2025.08.22
相手に”選択肢を与える”ことには困難が伴います。医師と患者さんも同じです。
専門性が高いことに関して、一般の方に選択肢を与えるためにはまず十分な説明と、その方の理解が必要になります。どんなに説明に努力をしたとしてもその方にわからない、と言われてしまえば理解していただくことに失敗しているのですから、その後の選択に誤りが生じる事態に陥りがちです。ですので医師にとって患者さんに選んでもらう、ことは大変です。専門知識を理解できるまで説明しなければなりませんから。医師は先生ではない。損が多く、得は少ない作業になります。
専門家は一般の方には理解が難しいことを判断するために存在しているのだから、その専門家が正しいと思うことを患者さんにも選ばせればいいのだ、と考える医師は実は多くいます。そしてそれが間違いとも言えません。むしろそれを望む患者さんもおられます。
ただこれを国民と政治家に置きかえればその危険性がわかると思います。国民には政治はわからない。政治家は政治をするために国民に選ばれて存在しているのだから、国民に理解など求めず、正しいと思うことをやればいいのだ。実際そう思っている政治家は多そうですね(笑)。
患者に医療はわからない。医師は国家試験に合格し、専門性が高く、理解のできない医療を実践するためにいるのだから、患者に理解を求めず、正しいと思うことをやればいいのだ。
こうなります。
ただこれは間違いです。現実 裁判では医療側が何度も敗北しています。
乳腺専門医から見て、治療のためには絶対に温存はできない、全摘すべきだ、そう判断して全摘術を施行した医師がいます。事実、全摘が施行されて、その患者さんは治癒されています。しかし温存の選択肢を提示してくれなかった、という点で後に訴訟が起こりました。この裁判は医療側が負けています。
裁判官は、「温存でも治癒できるという医師は世界のどこにもいませんか?」と医師に尋ねました。
乳腺を専門にする医師であれば、この症例を温存はしません。温存は危険すぎます。そう医師は反論しました。けれどもそれは裁判官への解答になっていません。「いませんか?」
いや、それは探せばいるかもしれません。しかしガイドラインからも、いまの医療の現状からも正しい選択とは思いません。
裁判官はこう言いました。「しかしその医師の意見を、患者さんには聞く権利がある。」
選択肢を奪ったことで、医師は敗北したのです。
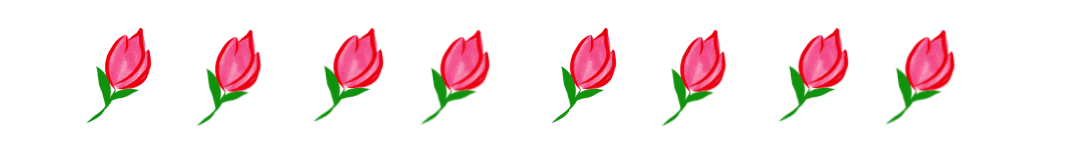
もちろん医療としてなにも間違いはなされていないので、賠償額は微々たるものでした。精神的な慰謝料のみです。ただ論争としては医師側の負けなのです。選ぶのは患者さんなのです。
ただこの話はほぼ詰んでいます。
医者の話を完全に理解できる一般の方は絶対いません。医師には話をしている内容の前提となる基礎知識があります。何十年もかけて学んできた医学の基礎があるから、それぞれの各論も理解できるのです。掛け算がわからない人に微分積分の説明はできません。理解なんてできません。
完全にはわからないことをいくら話をしても、患者さんに選んでもらったというのは言い過ぎです。必ず医師による誘導が介入しています。
前提が本当に長くなりました。すいません。
乳房再建は、乳がんの治療上絶対に必要なものではありません。
患者さんが選択して初めて施行される術式なのです。その意味において医師からの誘導も本来ありえません。患者さん以外に乳房が再建されることを望む主体はおられないからです。現実的には乳房全摘が必要とされた患者さんがそれを悲しみ、再建を希望されるところから話が始まります。医師はそれに伴う危険性、あり得る将来のデメリット、それを説明します。それでもなお患者さんが希望された時、それを施行しているはずです。
一言に乳房再建と言っても様々な方法があります。今回話題にしたいのはシリコンインプラントを用いた乳房再建です。失われた乳腺の代わりに皮下にシリコンインプラントを留置して乳房のふくらみを再現する方法です。

上に示したのがその表面がざらざらしたタイプのコヒーシブと呼ばれるシリコンバック、インプラントです。表面がざらざらしているのには理由があります。適度に皮膚と癒着し、中でゴロゴロと動かなくなるのです。つるつるしていると、中で動いて手術の時に決めた場所からズレていってしまうことがあります。一時はこのざらざらタイプが乳房再建の主役だったくらいです。
ところが最近になってこの”適度に癒着”することが問題であることがわかってきました。完全にはわかっていないのですが、この癒着する際に起こる刺激が免疫に悪影響するらしいのです。免疫細胞であるリンパ球がその刺激でがん化する、というリスクが認められたのです。ただしそれは本当に非常にまれなこともわかっています。
コロンビア大学アーヴィング医療センター アルフレッド・ノート博士を中心とするグループは2022年に米国における乳がんの未分化大細胞リンパ腫(BIA-ALCLと呼ばれています)の発生率を2000年から2018年において追跡調査し、発表しました。これを受けて、米国食品医薬品局(FDA)はすべての乳房インプラントに対して黒枠での警告を発令しました。FDAはインプラントに関連するものとして、未分化大細胞性リンパ腫に限らず、全てのリンパ腫に広げて今後追跡調査していくことを宣言したのです。これは大問題になりました。
Kinslow CJ, Kim DK, Lowe LS, Cheng SK, Yu JB, Kachnic LA, et al. Lymphomas of the Breast After Postmastectomy Implant-Based Breast Reconstruction. JAMA Network Open. 2025;8(8):e2525820.
米国のSurveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) データベースを用いて、2000 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日までの間に乳房切除術後のインプラント再建術を受けた女性を特定し、1年以上経過された方を追跡調査しています(1年以内であればもともと発症していた可能性があるため)。最終的に私たちは、乳がんと診断された約6万人の女性を対象に、平均で7年以上追跡調査を行いました。
私たちは、乳がんと診断された約6万人の女性を平均7年以上追跡しました。その結果、乳房に「悪性リンパ腫」と呼ばれるがんが15例見つかりました。特に「未分化大細胞型リンパ腫(ALCL)」というタイプは7例で、通常に比べておよそ40倍多く発生していました。その他のリンパ腫も8例見つかり、こちらは通常の約3倍でした。
診断されたリンパ腫には、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫や小リンパ球性リンパ腫といった種類も含まれており、5例は最初の乳がんとは反対側の乳房にできていました。乳がんの治療歴を見ると、放射線治療を受けていた人はいませんでしたが、化学療法を受けていた人が5人いました。
乳房にリンパ腫ができるまでの期間は、平均して約7年でした。発症のリスクを人口100万人あたりで換算すると、通常に比べて年間で10~15人程度多く発生していることになります。ただし、乳房以外にリンパ腫が増える傾向や、ホジキンリンパ腫という別のタイプの増加は見られませんでした。
また、乳房切除術を受けた人(インプラントを入れない場合)や、部分切除術を受けた人(放射線治療の有無に関わらず)では、乳房のリンパ腫が増える傾向は見られませんでした。
この研究では、乳房インプラントと、B細胞型やT細胞型と呼ばれる種類の悪性リンパ腫との関連が見つかりました。インプラントと関係があるとされてきた「未分化大細胞型リンパ腫(ALCL)」だけでなく、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫や小リンパ球性リンパ腫、末梢性T細胞リンパ腫といった他のタイプのリンパ腫でも、通常より発症のリスクが高くなっていました。
ALCLがインプラントと関連すると考えられる理由のひとつは、インプラントの周りで慢性的な炎症が起こり、そこで細胞が増えやすくなったり、酸素が足りない状態が続くことで、がん化が進みやすくなるためとされています。今回見つかった他のリンパ腫も、同じような仕組みで発症する可能性があります。
ただし、ここで強調すべき大事な点は、リンパ腫になる絶対的なリスクは非常に低いということです。ALCLもその他のリンパ腫も、起こる頻度はきわめてまれです。また、米国食品医薬品局(FDA)は、乳房インプラントに関連するがんとして「乳房の扁平上皮がん」も報告していますが、私たちの研究や他の研究では、乳房再建を受けた人にそのリスクの増加は確認されていません。
続きます>
ご予約専用ダイヤル
079-283-6103