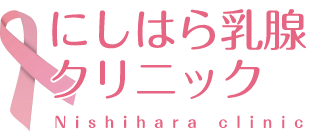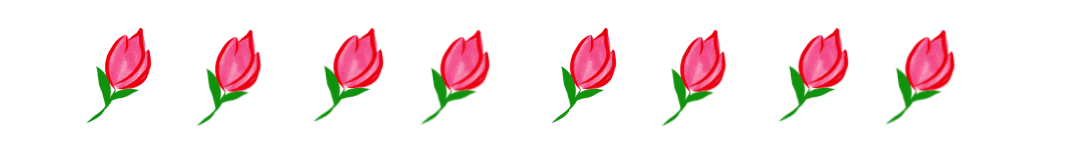線維上皮性病変(FEL)、線維腺腫(Fibroadenoma)、および良性葉状腫瘍(BPT)に関するガイドライン
総論・一般的なコメント(General / Overall Comments)
線維腺腫(fibroadenoma)は、女性乳腺における最も一般的な良性腫瘤の一つであり、主に生殖年齢の女性に発生します。この腫瘍はエストロゲン感受性(女性ホルモンに反応する)であり、初経以降に出現し、月経周期に伴って大きさが変動することがあり、妊娠中に増大し、閉経期には縮小(退縮)するといった特徴を示します。
世界保健機関(WHO)の乳腺腫瘍分類では、線維腺腫は以下の3つの病理学的亜型に分類されています:
Cellular(細胞型)/ Complex(複合型)/ Juvenile(若年型)
しかし、これらの型の臨床的挙動はほぼ同様であるため、管理方針も共通とされています。また、粘液型線維腺腫もこれらと同様の方針で管理可能です。
線維腺腫が悪性化する確率は非常に低く(0.1%未満)であることが報告されています。
(注:それならば細胞型(単純型と呼ばれたりします)、複合型(複雑型と言われたりします)と分ける必要がないではないかと思います。実際複合型では周辺に異型のある細胞が認められる際に指摘される分類であり、このタイプの線維腺腫では将来悪性化する(周囲にがんが発生する)可能性が、単純型よりも高いとする論文があります。ただ今回のガイドラインでは分類する必要はない、とする立場をとっています。)
診断時の画像検査
線維腺腫は、臨床診察で「可動性のある、境界明瞭な腫瘤」として触知されることが多く、またはマンモグラフィや超音波検査で発見されます。画像上では一般に、楕円形で境界明瞭、皮膚面に平行な位置にあり、内部が均一なエコーパターンを呈することが特徴です。
生検で線維腺腫と確定診断された場合、年齢に応じた通常の乳がん検診以外の追加画像検査は不要です。(注:とすれば線維腺腫を疑ったらとりあえず生検することになってしまいます。画像上線維腺腫と診断されたものすべてに生検は不要で、大部分は経過観察で十分でしょう。)
経皮的治療
コンセンサスパネル(専門家委員会)は、以下のような経皮的(切開しない)治療法について議論し、条件付きで推奨しました:凍結治療(cryoablation)/ 超音波ガイド下高強度集束超音波治療(HIFU)/ 吸引式生検装置による摘出(vacuum-assisted excision)
これらの手技は、乳腺超音波に熟練しており、経皮的介入手技に十分な経験を有する臨床医によって行われる場合に限り、選択肢として検討可能とされます。複数の研究(主に10年以上前の報告を含むが、一定の質を持つもの)では、3cm未満の線維腺腫に対して凍結治療を行うことで病変体積の縮小が得られ、患者満足度も高かったことが示されています。
そのため、専門家の意見として、コンセンサスパネルは以下のように結論づけています
「3.0 cm未満の線維腺腫で、目立つ瘢痕を残さずに摘出を希望する患者に対しては、これらの経皮的治療法を妥当な選択肢と考えることができる。」
線維腺腫の外科的切除の適応
針生検で線維腺腫と確定診断され、異型が認められない場合(注:複合型ではないかぎり)、管理方針は以下の複数の要素を考慮して決定されます:患者の年齢/ 随伴症状(疼痛や違和感など)/ 線維腺腫の大きさ・位置/ 増大速度(急速に大きくなるかどうか)/ 腫瘤の数(単発か多発か)/ 併存疾患/ 患者本人の希望
定型的切除の非推奨
生検で診断が確定し、画像と病理が一致しており、異型のない線維腺腫については、定型的な外科的切除は推奨されません。特に、乳房症状の改善を目的とした切除には注意が必要です。
外科的切除を行っても、乳房痛(特に周期性または両側性)が解消されないことが多いためです。
腫瘍サイズと切除の判断
腫瘍の大きさは病理学的悪性化リスクの信頼できる指標ではなく、特定のサイズを境にリスクが急増する「閾値」は存在しません。しかし、腫瘤が大きいほど、生検で十分にサンプリングされていない可能性が高く、最終病理で葉状腫瘍と診断される可能性が増します。
そのため、4〜6 cmというサイズを、明確なエビデンスに基づくものではなく、専門家の意見により、切除を検討すべき目安として採用しています。
経過観察と増大時の対応
線維腺腫はホルモン感受性であり、時間の経過とともに増大することがあります。パネルは、生検で確定診断された一致例に対しては定期的な画像フォローアップは不要としています。ただし、検診や診察で増大傾向がみられた場合には、スクリーニング画像や診断目的の追加撮影で経過を確認します。
一般的に、生検で良性と確定した線維腺腫では、6か月あたり20%以内の増大が「良性の範囲内」とされています。この20%を超える増大が認められた場合、再度の経皮的生検、または外科的切除を検討してよいとされています。
ただし、この増大率を一律の外科的切除基準として用いるべきではなく、実際の「良性範囲での増大」は年齢によって異なり、20%を超えることもあるため、臨床判断が重視されます。
多発性・両側性の病変
多発性または両側性で、明瞭な境界を持つ腫瘤については、切除を要しないことが示されています。これは、21施設で6000件以上の検診データを解析した国際多施設共同前向き研究によって確認されています。
要点まとめ
生検で確定し、異型のない(複合型でない)線維腺腫は基本的に切除不要。
症状改善目的での切除は慎重に。
4–6 cmを超える場合や急速な増大では切除を検討。
6か月で20%程度の増大は生理的範囲内。
両側・多発性病変は切除不要。
手術手技の実施
生検で診断が確定した線維腺腫を切除する際には、切開部位の選択と剥離方法に特に注意が必要です。切開部位を決める際には、以下の要素を総合的に考慮します:整容性/ 将来の授乳への影響/ 葉状腫瘍へのアップグレードの可能性(注:切除してみたら葉状腫瘍だったという可能性)/ 乳頭・乳輪複合体の感覚保持
線維腺腫の切除においては切除断端を陰性にすることは不要です。腫瘤は完全に摘出する必要がありますが、切断や細断は避けるべきです。手術中は頻繁に腫瘤を触診し、その位置を確認するとともに、腫瘤の一部を切断したり、不要に多くの正常組織を切除したりしないようにします。(これは前にも解説しましたが、外科医がきちんと取り切れたと判断していれば、病理の先生が顕微鏡で見て残っている可能性を示唆したとしても問題はない、ということです。ただ切除の際に、腫瘍をばらばらにして取り出したり、ちょっとずつ切って言ったりはするべきではない、ということです)
特に小児・思春期患者で線維腺腫を切除する場合、外科医は以下を心がける必要があります:正常な乳腺実質を温存すること/ 乳頭・乳輪複合体の周囲を避けて剥離し、乳腺芽および中心乳管を保護すること(注:これはある意味外科医の腕の見せ所です。こうしたことに配慮しながらきれいに腫瘍だけを残らず切除する、これこそ本領発揮です。)
非手術的管理
線維腺腫に対する薬物療法は、いくつかの研究で検討されています。これには無作為化比較試験も含まれます(注:きちんと正式な手続きを踏んでなされた研究もあるが、と前置きしています)。しかし、これらの治療法は臨床的効果が限定的であり、われわれのコンセンサスパネルは薬物療法の使用を支持しないという立場をとっています。
フォローアップケア
われわれ委員会は、生検で診断が確定した線維腺腫患者のフォローアップ方針を検討しました。結果として、以下について強い合意が得られました:
画像診断と病理診断が一致している線維腺腫に対しては、追加の画像検査や臨床フォローアップは不要である。これらの患者は、年齢に応じた通常の乳がん検診に戻ってよい。後ろ向き研究(247例、平均フォローアップ31か月)では、約80%の線維腺腫はサイズが安定していました。増大した症例のうち、切除されたもので、切除してみたら良性葉状腫瘍だったとなったいわゆるアップグレードは1例のみでした。
再受診の目安
以下の場合には、再度外科医への相談が推奨されます:線維腺腫が明らかに増大した場合/ 腫瘤のサイズが4〜6 cmに達した場合/ これらの状況では、外科的切除を含む対応方針を再検討します。(注:以前も触れましたが少なくとも米国では乳腺の自己チェックは高等教育に組み込まれており、しているのが常識です。)
多発性・両側性の病変
両側性または多発性で、画像上良性と判断される境界明瞭な腫瘤については、追加の画像検査や臨床フォローアップは不要であるとされています。この結論は、21施設で6,000件以上の検診データを解析した国際共同前向き研究によって裏付けられています。
まとめ
手術時は整容性・授乳機能・感覚温存に配慮。陰性マージンは不要。
薬物治療は効果が乏しく推奨されない。
生検で確定した線維腺腫は基本的に追加フォロー不要。
ただし、4〜6cmへの増大や急速な成長時は再評価を推奨。
多発・両側例は経過観察で問題なし。